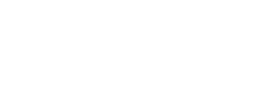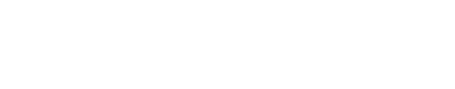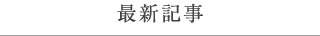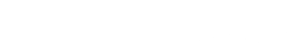住宅瑕疵担保履行法について
数年前に長期優良住宅の認定について、長期優良住宅仕様という紛らわしい宣伝文句で請負を契約しようとした工務店の提案書に、この瑕疵担保保険の保険料まで記載していました。私は施主に、支払いを拒否するようにアドバイスしました。結局、長期優良住宅の認定でトラブルとなり請負契約は白紙になり、事無きを得ました。
そんな工務店が存在しますので、住宅瑕疵担保履行法について説明したいと思います。
この法律に基づく資力確保措置については、発注者又は買主の意思にかかわらず義務となります。
新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されました。
新築住宅の請負人や売主に、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられました。
施 行日(平成21年10月1日)以降に新築住宅を引き渡した業者は、毎年3月31日と9月30日(年2回の基準日)時点での保険や供託の状況を、それぞれの 基準日から3週間以内に、建設業の許可や宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出る必要があります。
届出を行わない場合は、この法律に定める罰則の適用や業法(建設業法または宅地建物取引業法)に基づく処分の可能性がある他、基準日の翌日から50日を経過した日以降、新たな新築住宅の請負契約や売買契約を締結できなくなりますので、ご注意下さい。
なお、最初の基準日は、平成22年3月31日です。
資力確保措置として保証金の供託を行う場合、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任をカバーする必要があるため、基準日から過去10年間に遡って引き渡した新築住宅の戸数に応じて保証金の額を算定し、法務局等に供託することとなります。
ただし、新法による資力確保措置の施行日(平成21年10月1日)から10年間については、経過措置として、その施行日以後の引渡し戸数が供託金算定の対象となります。したがって、いきなり過去10年間に引き渡した戸数に対応した額を供託する必要はありません。
住宅瑕疵担保責任保険についての保険申込金の支払いにおいては、任意として事業者(建築会社)と施主のどちらかからでも支払うことは可能です。
上記、任意であることから、施主が支払いを拒否した場合、事業者は、保険の加入若しくは、供託をしなければなりません。義務は、どちらにあるか明白ですので、施主に負担を強いる建築会社には、くれぐれも注意してください。
家づくりの相談窓口
住宅建築コーディネーター事務所
住デザイン
078-963-5511
a.sakai@judesign.jp
http://judesign.jp/contact/
- 前の記事:長期優良住宅の認定を受けるには
- 次の記事:家主様を悩ませる共同住宅の空室対策