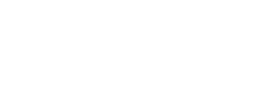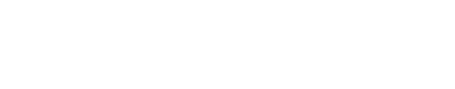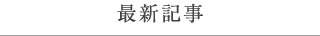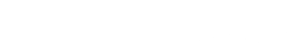2017年3月13日
家づくり 設計・施工一貫方式と設計・施工の分離発注について
設計・施工一貫方式と設計・施工の分離発注について
日本のゼネコンのほとんどが、設計・施工一貫方式を「売り」にしています。
そういった会社は、自社で設計することで、設計士と施工スタッフとの協議がスムーズに行われコストダウンやトラブルを少なくできるという触れ込みです。
では、実際はどうでしょうか。
確かに、その施工会社が特殊な工法や建材を使用して建築する会社なら、設計士も専門性が必要となりますので、あなたが、そういう建築物を考えるなら設計と施工は一貫のほうが良いと思います。
しかし、一般の工法であれば、設計士による見積もりチェックや入札を行うことで、コストダウンやトラブルを未然に防ぐことが出来ると思います。
監理をする場合も、チェックする立場の設計士が同じ会社の同僚になれば、厳しいチェックができるはずがないからです。
分離発注する場合のデメリットは、設計士も色々で、例えば「建築家」といわれるような自称、建築デザイナーは、費用を無視した作品を作る方がおられるので、注意が必要です。
また、設計士が設計の意図を施工会社に伝える時間が長くなり、施工までに多くの時間を費やす事例も少なくありません。
折角、コストダウンを目的に分離発注したのに、結局、コストが高くなるという事態は避けなければなりません。
あなたは、どのような建物を建てたいか、予算はいくらかといった希望を具体的にイメージ出来たら、いろいろな選択肢を模索しましょう。
そこで、中立な立場の住宅建築コーディネーターが必要になるのです。
住宅建築コーディネーターが、分かりやすく説明し、あなたの選択肢を増やします。
ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
家を建てる時、住宅建築コーディネイターが必要な13の理由 #11 欠陥住宅はなぜ建てられるのか ①
家を建てる時、住宅建築コーディネイターが必要な13の理由#12 欠陥住宅がなぜ、建てられるのか?②
- 前の記事:住デザインで古民家鑑定が出来ます
- 次の記事:1000スマイル神戸#564に参加しました。